中学受験に向けて過去問はいつから解くべき?過去問に関するよくある質問に回答!
最終更新日:2025/03/19
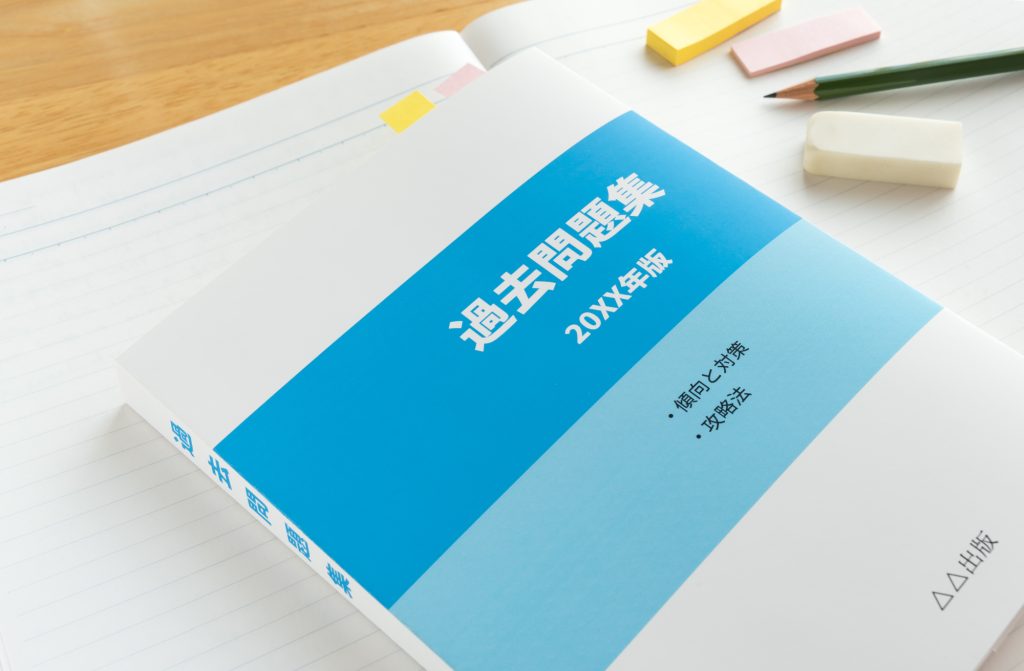
こんにちは!四谷学院個別指導教室の古川です。
中学受験に向け、過去問演習をいつから始めればよいのか、どのように進めればよいのかと悩む方は多いのではないでしょうか。
中には、限られた時間で効率よく勉強を進めるために、過去問に時間を割きたくないと考える方もいるかもしれません。
本記事では、過去問演習を始める適切な時期とその重要性について解説します。過去問に関する疑問を解消し、中学受験対策の土台を築いていきましょう。
目次
中学受験の過去問はいつからやるべき?

中学受験に向けた過去問演習は、小学6年生の9月頃から始めるのが一般的です。
早すぎても学習効果が薄れやすくなるため、早く始めればよいというわけではありません。
そのため、小学6年生の秋頃までは、中学受験に必要な学力の基礎を固め、知識を定着させることに集中するとよいでしょう。
基礎固めが終わってから過去問に取りかかると、その時点での学力や苦手部分なども把握しやすくなります。
過去問は過去何年分をやるべき?
勉強時間には限りがあるため、取りかかれる過去問の数も限られてきます。志望校が複数ある場合は、第一志望の過去問を優先して解くようにしましょう。
理想的な過去問の目安としては、以下のように進めるのがおすすめです。
- 第一志望校:直近10年分
- 第二志望校:直近5年分
- 第三志望校:直近3年分
ただし、社会のように時事問題を含む科目については、あまり古い過去問を使うのはおすすめできません。時事問題対策を考慮し、過去5年分を目安に解くのがよいでしょう。
また、近年出題傾向が変わった学校の場合、古い過去問は使用せず、現在の出題傾向に合った過去問を使用するのが鉄則です。
どうしても十分な勉強時間が確保できない場合でも、第一志望校は最低でも直近5年分の過去問を解いておくことが重要です。
中学受験における過去問活用の重要性

学校独自の問題が出題される中学受験では、過去問をそこまで重視していない方もいるかもしれません。
しかし、過去問を解くことは、受験校の出題傾向を把握したり、思考のパターンを増やしたり、知識の穴を埋めたりするためにも欠かせません。
ここからは、中学受験で過去問が重要視される3つの理由を詳しく解説します。
出題される問題の傾向がわかる
中学受験では、学校ごとに独自の試験問題が作られるため、受験校の出題傾向を把握しているかどうかで、合格率が大きく変わるといっても過言ではありません。
直近の過去問を解いていくと、毎年似たような問題が出題されている単元や、反対にほとんど出題されていない単元があることに気付くことがあります。
出題傾向を把握すれば、学習すべきポイントを見つけやすくなり、効率よく学習を進められるでしょう。
試験慣れができる
過去問を解くと、実際の試験問題に慣れることができます。特に、複数年分をこなすと試験慣れができるため、本番でも落ち着いて普段どおりの実力を発揮しやすくなります。
また、出題傾向を把握したうえで大問の数や記述問題の有無などがわかると、時間配分を考えておくこともできるでしょう。
自分の足りない部分がわかる
出題傾向がはっきりしている中学校の場合、過去問を多く解けば自分の苦手部分を明確にできます。
点数を落としやすい部分がわかれば、集中的に復習することで効率よく学力を上げられるでしょう。
一方で、基礎や応用力が身についていて得点が安定している場合は、ケアレスミスをなくす練習をしたり、より難易度の高い過去問に挑戦したりすることでさらなる高みを目指せます。
中学受験の過去問に関するよくある質問
以下では、中学受験の過去問についてよく寄せられる質問をまとめました。本格的な受験勉強に取りかかる前に、過去問についての理解を深めておきましょう。
過去問はどこで入手できる?
中学受験の過去問は、主に以下の方法で入手できます。
- 受験する中学校で配布されている過去の入試問題をもらう
- 書店で過去問題集を購入する
- 受験する中学校の公式ホームページや、過去問を掲載しているサイトからダウンロードする
過去問の配布や掲載方法は中学校により異なるため、本格的に受験勉強を始める前に早めに確認しておくことをおすすめします。
間違った過去問の復習方法は?
なぜ間違えたのか、誤解している部分がないかなどを都度確認しながら、正しい解答を導けるよう繰り返し問題を解きましょう。
教科ごとに復習ノートを用意しておくと、苦手部分の学習に役立てられます。
また、解答や解説が理解できない部分があれば、塾の講師や学校の先生などに質問して、わかりやすく説明してもらうことも大切です。
過去問を解く頻度はどれくらい?
科目ごとの得意不得意により一概にはいえませんが、各科目で3~5回ほどを目安に解くとよいでしょう。1年分をすべて解く方法以外に、苦手な大問に絞って解くなど工夫すると、応用力を身につけられます。
1年分を解ききる場合は、本番同様の環境や時間を意識すれば、実践的な試験対策になります。ただし、1日で全科目の過去問を解いたり、何年分も進めたりするのは、学習量が多すぎて負担になるためおすすめできません。
まとめ
中学受験の過去問演習は、小学6年生の9月頃を目安に始めるのがおすすめです。基礎固めを終えてから過去問に取りかかると、実践的な学力を身につけられます。
四谷学院では、各生徒の能力や学習の進度に合わせたオーダーメイドカリキュラムを作成し、1対1で細やかな指導を実施しています。
また、受験コンサルタントによる個々の進路相談や志望校対策にも対応しており、中学受験を目指す生徒を全面的にサポートできる点が魅力です。
四谷学院の個別指導について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
こんな記事も読まれています
前の記事 » 高校受験に向けた基礎固めのやり方(勉強法)とは?記憶を定着させるコツを解説
次の記事 » 中学受験における千葉御三家とは?それぞれの学校の特徴や合格のコツを解説


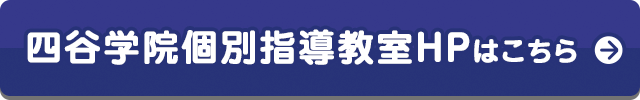
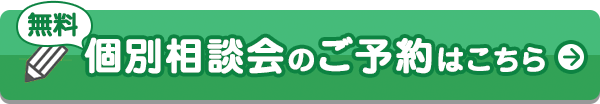

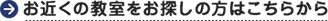
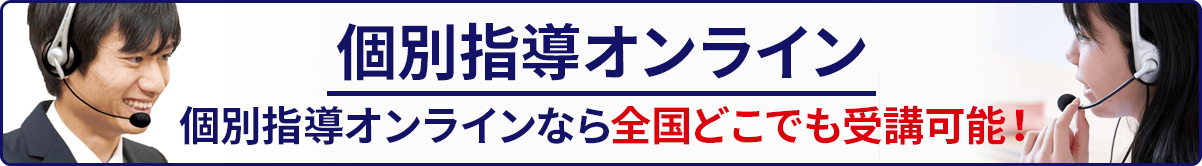

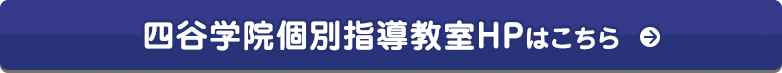
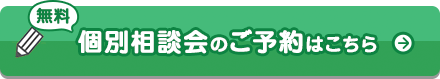
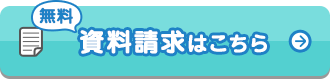
 高木:勉強に運動に何事にも全力で!人生は一度きりなので悔いのないように私と一緒に合格というゴールを決めよう!!
高木:勉強に運動に何事にも全力で!人生は一度きりなので悔いのないように私と一緒に合格というゴールを決めよう!!  古川:受験生や勉強に関するお悩みなど、役に立つ情報をたくさんお届けしますので、お楽しみに!
古川:受験生や勉強に関するお悩みなど、役に立つ情報をたくさんお届けしますので、お楽しみに!  津田:勉強を楽しむヒントを発信します。「勉強って楽しいかも!」と思えれば、学校も塾も毎日が楽しくなりますよ!
津田:勉強を楽しむヒントを発信します。「勉強って楽しいかも!」と思えれば、学校も塾も毎日が楽しくなりますよ!  佐久間:小学生・中学生のお子さんを持つ保護者の方を対象に、学校や勉強についてのよくある悩みを解決していきます!
佐久間:小学生・中学生のお子さんを持つ保護者の方を対象に、学校や勉強についてのよくある悩みを解決していきます!